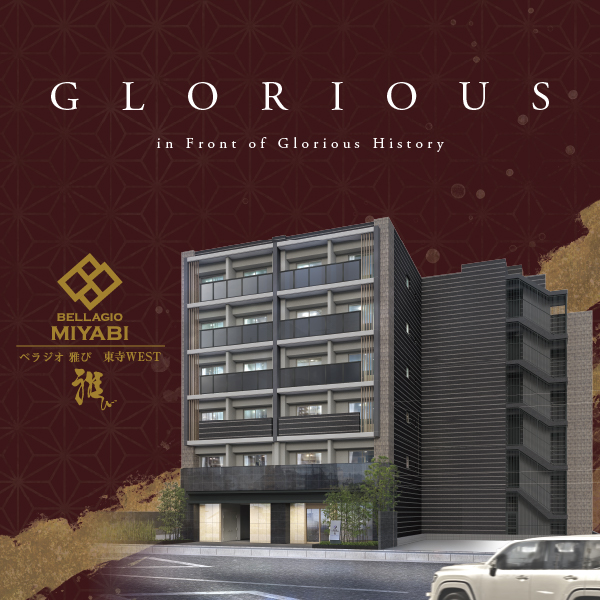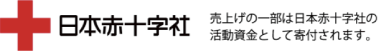磨かれた染色技法と扇絵師・宮崎友禅斎によって花開く「京友禅」
「京友禅」は有名ながら、その始まりはあまり知られていないかもしれませんね。
友禅という言葉は、江戸時代に京の町で人気の扇絵師として名をはせていた宮崎友禅斎の名前からとられたものです。
その当時、発達してきていた糊防染の技法を用いて友禅斎の扇絵風の模様を染めた着物が流行。
絵画のようにのびやかかつ華やかな模様を布に表現することができる糊防染の技法と、それまでの着物には見られなかった斬新なデザイン。
複雑で多彩な絵模様を自由に染めた着物は大いに人気を呼ぶこととなり、そうした人気にあやかって友禅染と呼ばれるようになったといわれています。
多くの製作工程を手仕事で仕上げる分業の伝統を受け継いで
「京友禅」は、制作工程だけで約15〜20程に分かれています。糸目糊置き、金彩や刺繍といった仕上げに見える部分だけではなく
技法を支えるために必要な工程も多くあります。
それぞれの工程で熟練の技と経験が求められ、一つでも失敗すれば製品にはなりません。
「京友禅」には非常に高い集中力と繊細な感覚が要求され、手仕事すべてが難しいといえるでしょう。
日々の仕事は容易ではありませんが、私たちは「京友禅」の美しさや手仕事に宿る美意識を伝えたいと考え、分業の手仕事を受け継いでまいりました。
現代の生活空間で、「見て楽しむ」アート「友禅ガラス」
伝統工芸をいかに日々の暮らしの中で楽しんでいただけるか。これは私たちが常に考えている課題です。着物の需要が減少する中で、「京友禅」の技術を現代のライフスタイルに合った形で提案することで、新たな市場を開拓し伝統の美を未来へ繋ぎたいという思いがありました。
「京友禅」を身につけていただくだけでなく、現代の生活空間で「見て楽しむ」アートとしての友禅、「友禅ガラス」をご提案しました。
今回の取り組みは、私たちにとっても新しい挑戦であり、大変よい経験となりました。これからも、伝統工芸の魅力を多くの方に届けられるよう、柔軟な発想で取り組んで行きたいと思います。